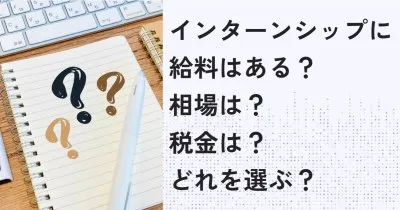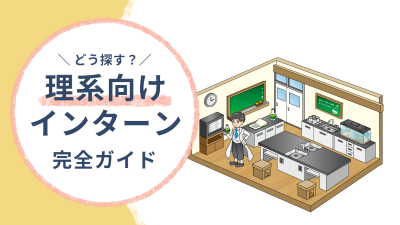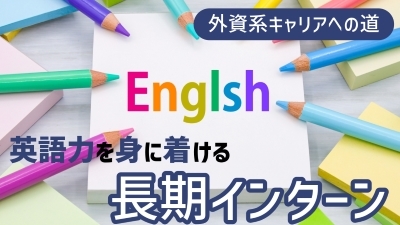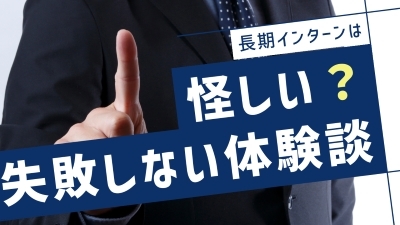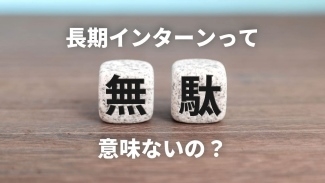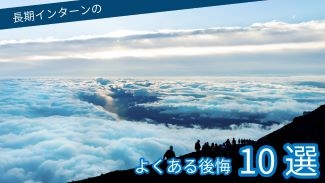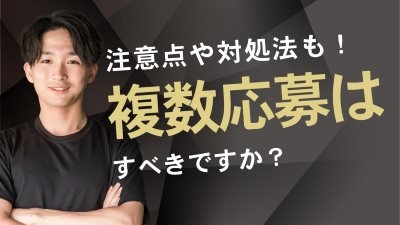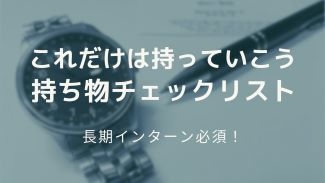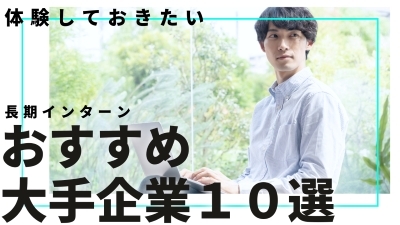インターンシップに参加する際、給料の有無は重要なポイントです。本記事では、オープンカンパニーから高度専門型まで、各タイプのインターンシップにおける給料の有無や相場、インターンシップ中の税金の扱いまでを詳しく解説します。無給のインターンシップが労働基準法違反となるケースや、アルバイトとの違いも含めて、就活生が知っておくべき情報を網羅的にお伝えします。読めば、自分に合った有給インターンシップの選び方が分かり、効率的なキャリア形成への第一歩を踏み出せます。
【結論】インターンシップは給料があるものを選んでおきたい
インターンシップを選ぶ際には、給料が支給されるものを選択することを強くお勧めします。その理由として、実務経験を積みながら収入を得られることに加え、企業側の本気度が見えやすいことが挙げられます。
特に長期インターンシップの場合、生活費や交通費などの経済的負担が大きくなります。給料が支給されるインターンシップであれば、これらの負担を軽減できるだけでなく、より実践的な業務に携わることができる可能性が高くなります。
有給インターンシップを選ぶべき3つの理由
第一に、企業の本気度が明確です。給与を支払う以上、企業側も人材育成に本腰を入れており、より実践的な業務を任せてもらえる可能性が高くなります。
第二に、労働者としての権利が守られます。有給インターンシップの場合、労働基準法が適用され、労災保険なども適用されるため、安心して業務に取り組むことができます。
第三に、就職活動において強みとなります。有給インターンシップは一般的に実践的な業務経験を積める機会が多く、これは就職活動時のアピールポイントとなります。
無給インターンシップのリスク
無給インターンシップには、以下のようなリスクが存在します。経済的な負担が大きい、実践的な業務経験が得られにくい、労働者としての権利が保障されないなどの問題があります。
特に注意が必要なのは、いわゆる「ブラックインターンシップ」です。無償で労働力として活用されるだけで、本来のインターンシップの目的である教育的効果が得られない可能性があります。
選考直結型インターンシップにおける給与の重要性
近年増加している選考直結型インターンシップでは、特に給料の有無に注目する必要があります。給料が支給されるインターンシップは、その後の本採用に向けても前向きな評価につながりやすい傾向があります。
大手企業の例を見ると、ソフトバンク、リクルート、DeNAなどでは、インターンシップ生に対して時給1,000円以上の給料を支給しており、これは企業の人材育成に対する投資意欲の表れと言えます。
インターンシップ探しのポイント
インターンシップを探す際は、就職情報サイトやキャリアセンターを活用しましょう。マイナビ、リクナビ、キャリタス就活などの主要就職サイトでは、給料条件で絞り込み検索が可能です。
また、インターンシップ選びの際は、給料の有無だけでなく、業務内容、期間、勤務時間なども総合的に考慮することが重要です。特に自身のキャリアプランに合致した業界や職種を選択することで、より効果的なインターンシップ経験となります。
インターンシップの種類と給料との関係性
今回、国の省庁でインターンシップについての整理がなされました。新しいタイプとしては、実施形態や目的によって大きく4つのタイプに分類されます。それぞれのタイプによって給与の有無や金額に違いがあり、学生の皆さんが参加を検討する際の重要な判断材料となります。
タイプ1.オープンカンパニー
企業説明会の発展形として実施される1日〜3日程度の短期インターンシップです。主に夏季や春季の長期休暇中に開催され、業界研究や企業理解を目的としています。
給与に関しては、ほとんどの場合が無給となっています。ただし、交通費支給のある企業も増えており、特に地方から参加する学生への配慮として、交通費や宿泊費を支給するケースも見られます。
タイプ2.キャリア教育
1週間から2週間程度で実施される、職業観や就業意識を育むことを目的としたインターンシップです。実際の業務体験よりも、グループワークやワークショップを通じた学びが中心となります。
給与面では、基本的に無給が一般的です。ただし、大手企業を中心に日当1,000円から3,000円程度の実費支給を行う企業も出てきています。特に製造業や建設業では、現場での実習を伴うケースもあり、その場合は安全管理の観点から傷害保険への加入費用を企業が負担するケースが多いです。
タイプ3.汎用的能力・専門活用型インターンシップ
1ヶ月から3ヶ月程度の中長期で実施され、実践的な業務経験を通じて社会人基礎力を養成することを目的としています。営業同行やマーケティング企画の立案など、実務に近い経験ができます。
給与については、時給800円から1,200円程度の有給インターンシップが主流となっています。特にIT企業やベンチャー企業では、プログラミングスキルやデザインスキルを活かせる職種において、時給1,500円以上の待遇を提示するケースも増えています。
タイプ4.高度専門型インターンシップ
3ヶ月以上の長期で実施される、高度な専門性を要する業務を経験できるインターンシップです。主に理系の大学院生や、特定の専門スキルを持つ学生が対象となります。
給与水準は最も高く、月給15万円から30万円程度の待遇が一般的です。研究開発職では成果に応じて報奨金が支給されるケースもあります。大手製薬会社や半導体メーカー、システム開発企業などで多く見られます。
大学の単位認定を受けるインターンシップはどのタイプ?
単位認定の対象となるインターンシップは、主にタイプ2とタイプ3に該当します。大学によって認定基準は異なりますが、一般的に以下の条件を満たす必要があります:
・事前・事後学習が設定されていること
・一定期間以上(多くは5日間以上)の実習であること
・実習記録やレポートの提出があること
・企業からの評価書が提出されること
単位認定型インターンシップの場合、給与の有無は大学の方針によって異なります。一部の大学では教育プログラムとしての性質を重視し、有給のインターンシップを単位認定の対象外としているケースもあります。
有給インターンシップとアルバイトの比較
多くの学生が悩むのが、インターンシップとアルバイトの選択です。両者には明確な違いがあり、目的に応じて使い分けることが重要です。ここでは実践的な視点から、有給インターンシップとアルバイトを詳しく比較していきましょう。
給料面での差はほとんどない
有給インターンシップとアルバイトの時給を比較すると、実は大きな差はありません。一般的な事務職のアルバイトが時給1,000円〜1,200円程度であるのに対し、有給インターンシップも同程度の時給設定が多く見られます。
ただし、大手企業のインターンシップでは時給1,500円以上の案件も存在し、IT業界では2,000円を超えるケースも珍しくありません。特にプログラミングスキルを活かせる職種では、アルバイトよりも高い時給が期待できます。
学業とのバランスについて
アルバイトは比較的自由なシフト調整が可能で、授業の空き時間に入れやすい特徴があります。一方、有給インターンシップは平日の決まった時間帯での勤務が求められることが多く、学業との両立には慎重な時間管理が必要です。
特に研究室に所属する理系の学生は、インターンシップの参加にあたって指導教官との事前相談が推奨されます。多くの大学では学業に支障が出ない範囲でのインターンシップ参加を推奨しています。
目的や仕事内容に大きな違いがある
最も重要な違いは、その目的と仕事内容です。アルバイトは単純作業や定型業務が中心で、収入を得ることが主目的となります。一方、有給インターンシップは将来のキャリアを見据えた実践的な業務経験を積むことが目的です。
<アルバイトの特徴的な業務内容>
飲食店での接客、コンビニエンスストアでのレジ打ち、塾での講師など、比較的簡単な研修で始められる仕事が中心です。責任は限定的で、マニュアルに沿った作業が求められます。
<有給インターンシップの特徴的な業務内容>
マーケティング戦略の立案、プログラミング開発、商品企画など、正社員が担当するような本格的な業務に携わることができます。また、プロジェクトの一員として成果を求められる場面も多くあります。
<キャリア形成における違い>
有給インターンシップでは、業界知識の習得や、ビジネススキルの向上、人脈形成など、将来のキャリアに直結する経験を得られます。特に、就職活動時のエントリーシートや面接で、インターンシップでの経験を具体的にアピールできることは大きなメリットとなります。
また、有給インターンシップは採用直結型のものも多く、優秀な成績を収めれば本採用への道が開かれる可能性もあります。一方、アルバイト先での正社員採用は、一部の業界を除いてそれほど一般的ではありません。
有給インターンシップの給料相場
有給インターンシップの給料相場は、業界や職種、企業規模によって大きく異なります。一般的な相場を把握することで、インターンシップ選びの参考にすることができます。
業界別の給料相場
IT業界では時給1,200円〜2,000円が一般的で、プログラミングスキルやAI関連の知識がある場合は時給2,500円以上になることもあります。金融業界では大手銀行や証券会社で時給1,500円前後、コンサルティング業界では時給1,800円〜2,500円程度となっています。メーカーは時給1,000円〜1,500円、小売業界では時給1,000円前後が相場です。
職種別の給料相場
エンジニア職は時給1,500円〜3,000円と高めの設定が多く、特に機械学習やクラウド技術に精通している場合は上限近くまで期待できます。営業職は時給1,200円〜1,800円、マーケティング職は時給1,300円〜2,000円程度です。人事職は時給1,000円〜1,500円、デザイナー職は時給1,200円〜2,000円が一般的です。
<長期インターンシップの場合>
3ヶ月以上の長期インターンシップでは、月給制を採用している企業も多く見られます。一般的な相場は月給15万円〜25万円で、週3日程度の勤務を想定しています。優秀な学生の場合、月給30万円以上の好条件を提示する企業もあります。
<短期インターンシップの場合>
1日〜1週間程度の短期インターンシップでは、日給制を採用している企業が多く見られます。一般的な相場は日給8,000円〜12,000円です。ただし、1日限りのインターンシップは無給のケースも多いため、事前に確認が必要です。
企業規模による給料の違い
大手企業(従業員1,000人以上)では時給1,300円〜2,000円が一般的です。中堅企業(従業員300人〜1,000人未満)は時給1,100円〜1,800円、中小企業(従業員300人未満)では時給1,000円〜1,500円程度となっています。ただし、ベンチャー企業の中には大手企業以上の給料を支給するケースもあります。
地域による給料の違い
東京都内では時給1,200円〜2,000円が一般的ですが、大阪や名古屋などの大都市圏では時給1,000円〜1,800円、地方都市では時給900円〜1,500円程度となっています。ただし、リモートワークが可能なIT系のインターンシップでは、地域による給料の差が少なくなる傾向にあります。
就業時期による給料の変動
夏季(8月〜9月)や春季(2月〜3月)の繁忙期は、通常期と比べて時給が100円〜300円程度上乗せされるケースがあります。また、土日祝日の勤務では25%程度の割増賃金が適用される企業も多く見られます。
選考プロセスによる給料の違い
一般公募型のインターンシップは比較的低めの時給設定が多いのに対し、スカウト型や推薦型のインターンシップでは高めの時給が設定されることが多くなっています。特に、大学院生や高度な専門性を持つ学生向けのインターンシップでは、一般的な相場よりも高い給料が提示されることがあります。
有給インターンシップの給料にかかる税金
有給インターンシップで得た収入にも、一般的な給与所得と同様に税金がかかります。具体的には所得税と住民税が課税対象となり、収入額によっては社会保険料も発生する可能性があります。
所得税の基礎控除と課税対象
給与所得の基礎控除額は年間38万円となっています。つまり、年間の収入がこの金額を超えない場合は、所得税は課税されません。ただし、複数のインターンシップやアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての収入を合算して判断されます。
源泉徴収の仕組み
有給インターンシップの場合、企業は給料から源泉徴収を行います。源泉徴収税額は、給与所得の源泉徴収税額表に基づいて計算されます。例えば、月収10万円の場合、源泉徴収額は約2,060円程度となります。
住民税の扱い
住民税は前年の所得に基づいて課税されます。学生の場合、多くは扶養控除の対象となっているため、年収が103万円を超えないように注意が必要です。これを超えると、保護者の扶養から外れる可能性があります。
社会保険の加入基準
インターンシップ期間中の労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上)となる場合、社会保険への加入が必要となります。この場合、給料から健康保険料と厚生年金保険料が控除されます。
<健康保険料の計算方法>
健康保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて計算されます。保険料率は都道府県によって異なりますが、概ね9〜10%程度で、事業主と折半となります。
<厚生年金保険料の負担>
厚生年金保険料は18.3%で、これも事業主との折半となります。つまり、給料から約9.15%が控除されることになります。
確定申告の必要性
通常、給料収入のみの場合は確定申告は不要です。ただし、年末調整を受けていない場合や、複数の収入源がある場合は、確定申告が必要となる場合があります。
税金控除の活用方法
インターンシップに参加する際の交通費は、非課税となる通勤手当として支給される場合があります。また、実費支給される場合は課税対象外となります。研修に必要な備品代なども、会社負担である場合は課税対象外です。
奨学金との関係性
日本学生支援機構の奨学金を受給している場合、収入が一定額を超えると支給額に影響が出る可能性があります。特に第一種奨学金の場合、年収が上限を超えると返還の対象となることがあるため、事前に確認が必要です。
まとめ
インターンシップにおいて、給料の有無は重要な選択基準の一つです。
有給インターンシップは時給1,000円から1,500円程度が一般的で、アルバイトと大きな違いはありません。
ただし、キャリア教育型や1日だけの企業見学型は基本的に無給となります。就業体験を伴う長期インターンシップでは、最低賃金法の観点から有給であることが望ましく、実務経験も得られるため、可能な限り有給のインターンシップを選択することをお勧めします。
税金面では、給与収入が103万円を超えない限り、所得税の課税対象にはなりませんが、雇用保険や社会保険の加入要件には注意が必要です。